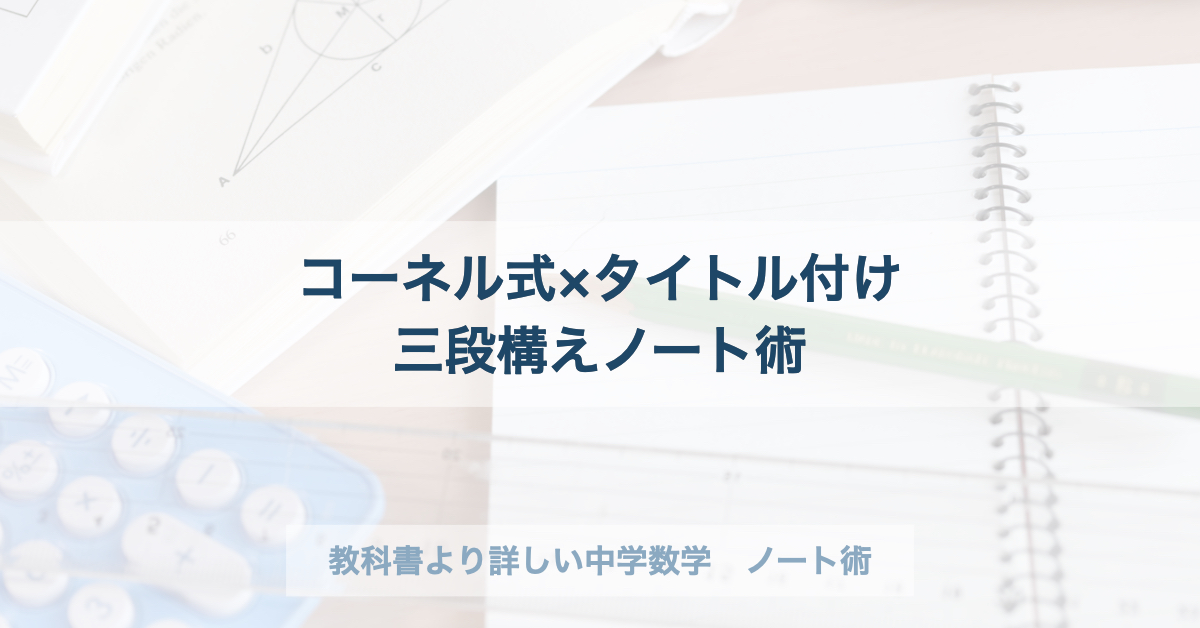ノートをがんばって書いたのに、あとで見ると「どこが大事?」と迷ってしまうこと、ありますよね。そんなときに役立つのが「コーネル式ノート」と「タイトル付けノート術」です。ページの左にキーワードや質問、右に授業のメモ、下に短い要約。さらに一番上に、そのページのゴール(何ができるようになるか)をはっきり書きます。これで、授業中に集中しやすく、次の日の復習もテスト前の見直しもスムーズになります。
コーネル式ノートの基本
-
- 左は「質問」、右は「メモ」、下は「30秒で言える要約」
- 流れは「授業前に準備→授業中に書く→24時間以内に整える」
- 左は単語ではなく「問いの文」にする
- 下は「結論→理由→注意点」を3行でまとめる
コーネル式ノートは、ただのレイアウトではなく「使い方」まで決まっています。授業の前に、教科書の見出しやプリントから「今日のテーマ」や「わからないこと」を左の欄に下書きしましょう。こうすると、授業中に「どこを聞けばいいか」がわかります。授業中は右の欄に、先生が強調したことや例、図や式のポイントを短い文で書きます。言葉はなるべく「何を、どうする」の形にすると、あとで読み返しやすいです。
左の欄は、ただの単語のメモではなく、「問い」にします。例えば「密度の定義」ではなく「密度は何を割って求める?」のように、疑問形で1文にしましょう。似ている言葉は、ちがいをたずねる問いにします。「拡散と対流のちがいは?」のように書くと、テスト前に力になります。
授業のあと24時間以内に仕上げます。左の欄を「問いの文」に整え、似ている内容は1つにまとめます。右の欄で足りない理由や条件があれば、1行だけ書き足します。下の欄は3行で要約します。1行目は結論。2行目は理由やしくみ(キーワードを2〜3個)。3行目は注意点や条件です。たとえば「結論:二次関数の最大と最小は平方完成で考える。理由:頂点がすぐわかり、範囲の問題に強い。注意:決められたxの範囲の端も必ず調べる」のように、30秒で言える短さが目安です。
最後にチェックです。右を隠して、左の問いに口で答えられるか。反対に左を隠して、右のメモから問いを思い出せるか。下の3行を読むだけで、友だちに30秒で説明できるならOKです。
タイトル付けノート術
- 1ページに1つのゴールをはっきり書く
- タイトルは型を使うと書きやすい
- 大事な言葉は先頭に。余分な言葉は減らす
- タイトルと本文は中身をそろえる
タイトルは、そのページの看板です。「何ができるようになるか」を一文で書きます。例えば「二次関数の最大最小|平方完成→軸→範囲」「弱酸のpHの出し方|近似の条件→式→例」のように、ゴールと手順がひと目でわかるとよいです。型も使えます。結論型「○○はこう考えると早い|理由→手順→例」、手順型「○○のやり方|1→2→3」、比較型「○○と□□のちがい|定義→場合分け→まちがえやすい所」、チェック型「テスト前チェック|ここだけは落とさない○項目」などです。
検索しやすくするため、重要なキーワードを先頭に置き、長すぎる部分はカットします。学校名などの固有名詞より、教科の言葉(概念名)でそろえると見つけやすいです。タイトルと本文のつながりも大切。左の問いはタイトルの下の項目に対応させ、下の要約1行目はタイトルの言いかえになるようにすると、復習の道すじが短くなります。
融合レイアウトの設計図
- 流れは「タイトルでゴール宣言→左に問い→右に理由と例→下で30秒要約」
- 授業前3分で「タイトル案・左の枠(3〜5本)・右の柱」を下書き
- 授業中は右メイン、左に思いついた疑問を足す。図や式は矢印で関係を見える化
- 授業後10分で左を問い文に、右を少し補強、下を3行にまとめる
まず授業前に3分だけ準備します。タイトル案でゴールを一文にして、左の欄には「定義」「性質(ポイント)」「手順」「例外」「まちがえやすい所」などの枠を3〜5本つくります。右の欄は、小さな見出しの柱を薄く書いておき、書く場所を決めておきます。
授業中は右の欄に大事なことと例を短い文で書きます。先生が「ここ出るよ」と言った所は印(★や!)で目立たせます。左の欄には、そのとき浮かんだ疑問もメモします。図や式は右の近くに置き、矢印で「原因→結果」や「手順の流れ」を見えるようにすると、後で理解しやすくなります。「事実→理由→例」の順に並べると、読み返すときに迷いません。
授業後は24時間以内に仕上げます。左の欄は必ず「問いの文」に整え、似た問いは1つにまとめます。右の欄は、足りない理由や条件を1行だけ足し、まちがえやすい境目には赤で印をつけます。下の欄は3行のテンプレで「結論」「理由(キーワード2〜3)」「注意点」を入れます。長くなったら、意味の変わらない言い回しから短くしましょう。30秒で言えるとちょうど良いです。
復習するときは「左→右→下」の順番です。左の問いだけを見て口で答え、つまったら右のその部分だけを確認。最後に下の3行を読んで、結論を頭に固定します。よくある失敗は、右が「写すだけ」になること、左が「単語メモ」になること、下が「長くなりすぎる」こと。これらは「授業前の左の下書き」「疑問形で書く」「3行テンプレを守る」で防げます。
使い回しやすい最小テンプレはこれです。
- タイトル:____|__→__→__
- 左:定義は?/なぜそうなる?/いつ使う?/例外は?/どこでまちがえやすい?
- 下:結論__/理由__・__/注意__
復習の進め方
- 翌日5分:左の問いだけで口頭チェック。迷った所にチェック印
- 3日後10分:チェックの所だけ右と見比べる。下の1行を言い換えて精度アップ
- 1週間後15分:左の問いを順番をバラバラにして答える(順番に頼らない練習)
- 横断復習は、タイトルの一覧→左だけの束ね読み→弱点だけを集中
翌日は、まず左の問いをテンポよく答えます。迷った問いにチェックをつけておきます。3日後はチェックの所だけ右のメモと見比べ、下の1行を言い換えて、より正確にします。1週間後は問いの順番をバラバラにして答え、暗記の順番に頼らない力をつけます。単元が広いときは、タイトルだけの一覧で全体を見てから、左の問いだけを続けて読んで弱点を見つけると効率が良いです。
テスト前にチェックリストとして活用
- 左の問いをそのままチェックリストにする(□できる/△あやしい/×できない)
- 48〜24時間前:×だけ右を見直し、下の要約を最新に
- 24〜12時間前:△を口頭で30秒説明できるか確認
- 直前:□だけサッと流し読み。新しいことには手を出さない
テスト前は、新しいことを増やすより「穴をふさぐ」ことが大切。左の問いをチェックボックスにして、×は右のメモで理由を確認し、下の3行を今の理解に合わせて更新します。△は30秒で説明できるかで仕上がりを判断します。直前は□だけを見て、頭の中の道を温めるイメージで整えましょう。タイトル一覧も使って、出題範囲のぬけがないかを最後にチェックすると安心です。
まとめ
最初にタイトルでゴールを決め、左で問いを立て、右で理由と例を書き、下で30秒にまとめる。この形にそろえるだけで、授業の理解からテスト前の見直しまでが一つの道になります。まずは今週、テンプレどおりに1ページ作ってみてください。左の問いだけで答えられる感覚が出てきたら、勉強がぐっと進みやすくなります。