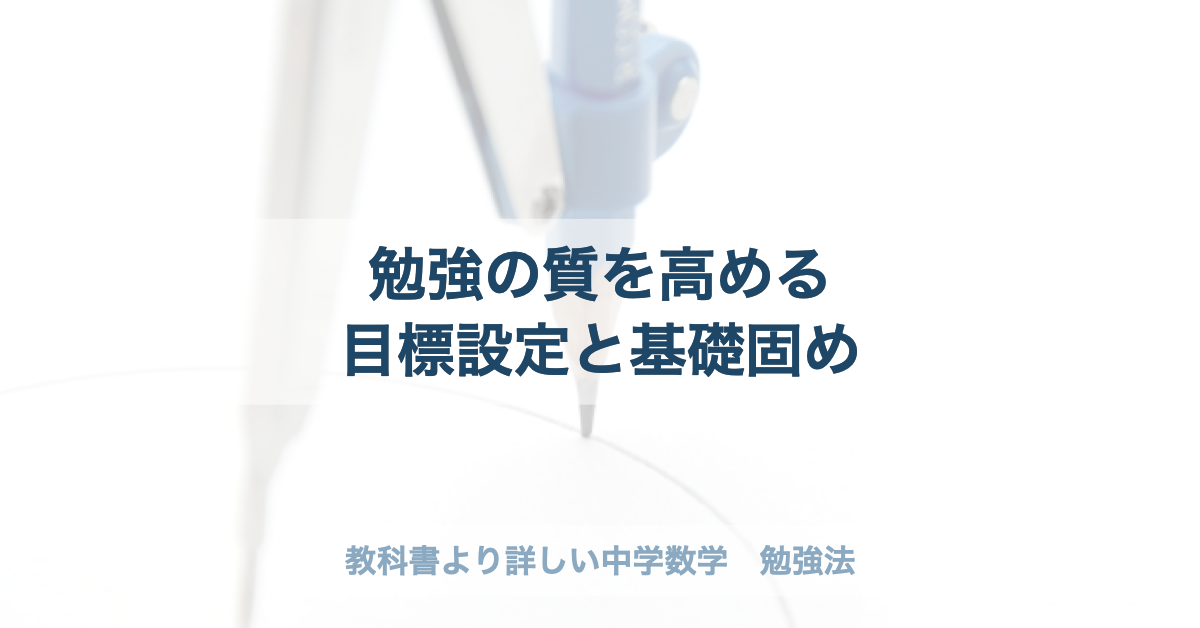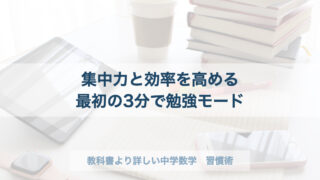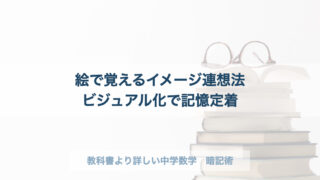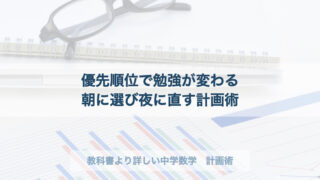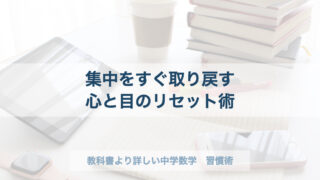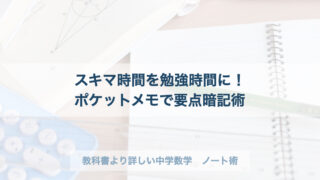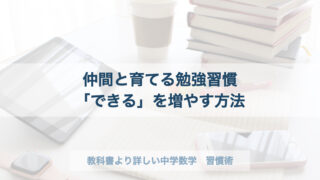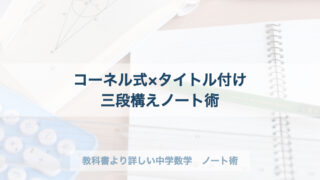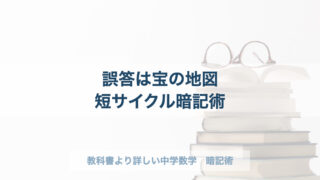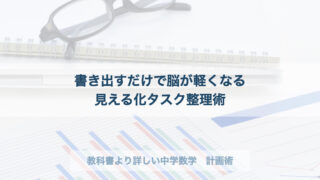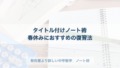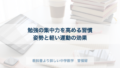はじめに
「テストが近いけど、勉強する気になれない」「がんばってるはずなのに、なかなか点数が上がらない」——そんなふうに感じたことはありませんか?
中学生になると、勉強の内容はどんどん難しくなり、教科数も増えてきます。部活動や友達との付き合いもある中で、「なんとなく勉強しているだけ」では、なかなか成果が出ないのが現実です。
でも安心してください。**大事なのは、「目標を持つこと」と「基礎を大切にすること」**です。
この2つを意識するだけで、勉強のやる気も成績もぐんと伸びるようになります。
この記事では、中学生にとってとても大事な「目標の立て方」と「基礎の勉強法」について、分かりやすく紹介していきます。どんな教科でも使える工夫もたっぷり紹介するので、ぜひ最後まで読んでみてください。
勉強に目標が必要な理由
「とりあえず宿題をやる」「親に言われたからワークを開いた」——こうした理由だけで勉強をしていても、なかなか成果は出ません。
自分で「このために勉強する!」という目的を持つことが、やる気や集中力を上げるカギになるのです。
たとえば、「次の数学のテストで80点以上をとる!」という目標があれば、苦手なところを重点的に勉強するようになったり、計画的に問題集を進めたりできます。目的がはっきりすると、毎日の勉強が意味のあるものになります。
目標を持つとこんなに変わる!
- 勉強に前向きになれる
- 自分がやるべきことがはっきりする
- 成績が上がったときの達成感が大きくなる
- 「できた!」の経験が自信につながる
- 目標に向かって努力する力が身につく
中学生にぴったりな目標の立て方
目標を立てるときは、「わかりやすくて、実現できそうなこと」から始めるのがコツです。はじめから「1位になる!」と大きすぎる目標ではなく、自分が少しがんばれば届きそうな目標を決めると、達成しやすくなります。
たとえばこんな目標が立てられます
- 「次の英語のテストで80点をとる」
- 「理科のワークをテスト1週間前に終わらせる」
- 「毎日漢字を10個ずつ覚える」
- 「2学期は3教科の平均を70点以上にする」
- 「将来◯◯になりたいから、そのために理科をがんばる」
目標は、「短期間で達成できる目標」と「長い目で見て取り組む目標」に分けると、バランスよく勉強できます。
目標を見える形にすると、続けやすくなる
目標は立てただけでは意味がありません。いつでも目に入るようにしておくことが大事です。たとえば、
- ノートの最初のページに書いておく
- 机の前や壁に紙を貼る
- スマホのメモアプリに登録する
- カレンダーに毎日チェックをつけて記録する
このようにすることで、毎日「自分が何を目指しているのか」が自然と意識できます。
特に、テスト前は見返すことで、やる気のスイッチが入りやすくなりますよ。
目標をかなえるための計画を立てよう
「どうすればその目標が達成できるか」を考えて、勉強の計画を立てることもとても大切です。無理のないスケジュールで、「いつ」「何を」するかを決めておけば、毎日の勉強がスムーズに進みます。
たとえば、「英語で80点以上とる」ことが目標なら、
- 1週目:基本の文法(be動詞・一般動詞)を復習
- 2週目:教科書の重要単語を覚える
- 3週目:学校のワークを終わらせる
- テスト前:プリントで演習、間違えたところをやり直す
このように、逆算して予定を立てておくと、安心して勉強に集中できます。
達成できたら、しっかり自分をほめよう!
目標が達成できたら、「よくがんばった!」と自分をしっかり認めてあげましょう。ごほうびを用意するのもOKです。たとえば、「ワークを1週間前に終わらせたら、好きなマンガを1冊読んでいい」など、自分のがんばりが楽しみに変わる工夫も大切です。
こうした達成感の積み重ねが、次のチャレンジへのやる気につながります。
基礎ができていないと、応用がうまくいかない
目標があっても、基礎ができていなければ、テストで思うように点数は取れません。
どんな教科でも、「基礎=土台」がしっかりしていることが、とても重要です。
たとえば、数学で計算ミスをするのは、たいてい「四則計算(+−×÷)」や分数の扱いが不安定だからです。基礎がしっかりしていれば、難しい問題も安心して取り組むことができます。
数学の基礎力を高めよう
中学数学では、「正負の数」「文字式」「方程式」「比例・反比例」「図形」など、1年生から3年生にかけて少しずつレベルが上がっていきます。でも、どれも最初の内容とつながっています。
- 正負の数が苦手だと、文字式の計算でミスしやすい
- 方程式のルールがあいまいだと、文章題が解けない
- 図形の面積・体積があやふやだと、応用問題に時間がかかる
だからこそ、「ちょっとあやしいな」と思ったら、基本に戻って復習することが大切です。
基礎の見直しはこうやろう!
- 自分の苦手を知る
教科書・ワーク・テストの間違いを見て、どこが苦手かを確認します。
- 基礎問題を何度も練習
まずは簡単な計算や確認問題をくり返して、スラスラ解けるようにしましょう。
- なぜそうなるかを考える
ただ覚えるだけではなく、「なぜこうなるの?」と考えてみることが、理解を深めます。
楽しく続けるための工夫
基礎の勉強は地道ですが、工夫すれば楽しく続けられます。
- タイマーを使ってタイムアタック式に解いてみる
- 友達と問題を出し合って競争する
- 学習アプリや動画で楽しく理解を深める
そして、「できたらカレンダーに◯をつける」「10ページ終わったらシールを貼る」など、目に見える記録をつけると達成感がわきやすくなります。
理科(化学・物理分野)でも基礎が大事!
理科の中では、化学や物理の分野に苦手意識を持っている人が多いかもしれません。でも、これらの分野も、基礎をしっかり理解すれば楽しくなってきます。
- 化学分野では「物質の性質」「状態変化」「溶解」「中和」などの基本をしっかり覚える
- 物理分野では「力のはたらき」「圧力」「電流」「光や音」などの法則を理解する
意味がわからないまま公式だけを覚えても、問題は解けません。なぜそうなるのかを、図やイラストで理解することがポイントです。
社会(日本の歴史)は「流れ」をつかもう
社会の中でも、日本の歴史は覚えることがたくさんあって苦手に感じる人も多いです。でも、ただ用語や年号を丸暗記するのではなく、「時代の流れ」を理解すると、ずっと楽に覚えられるようになります。
- 大きな時代の流れ(縄文→弥生→古墳→奈良…)をつかむ
- 「なぜその出来事が起きたのか」を考えてみる
- 教科書のまとめ・年表をノートに書き写して整理する
たとえば「明治維新」や「戦後の改革」など、大きな転換点を中心に覚えていくと、全体像がつながって理解しやすくなります。
まとめ
勉強がうまくいくようになるには、「目標をはっきりさせること」と「基礎をしっかり固めること」がとても大切です。
- わかりやすくて実現しやすい目標を決めよう
- 毎日目にする場所に目標を書いて、やる気をアップ!
- 勉強の計画を立てて、こつこつ取り組もう
- 基礎ができていないところは戻って復習しよう
- 楽しく続ける工夫をしながら、できることを少しずつ増やしていこう
今日から、「目標を持って、基礎を大切にする勉強法」を始めてみてください。
小さな一歩が、きっと大きな自信と成果につながります。