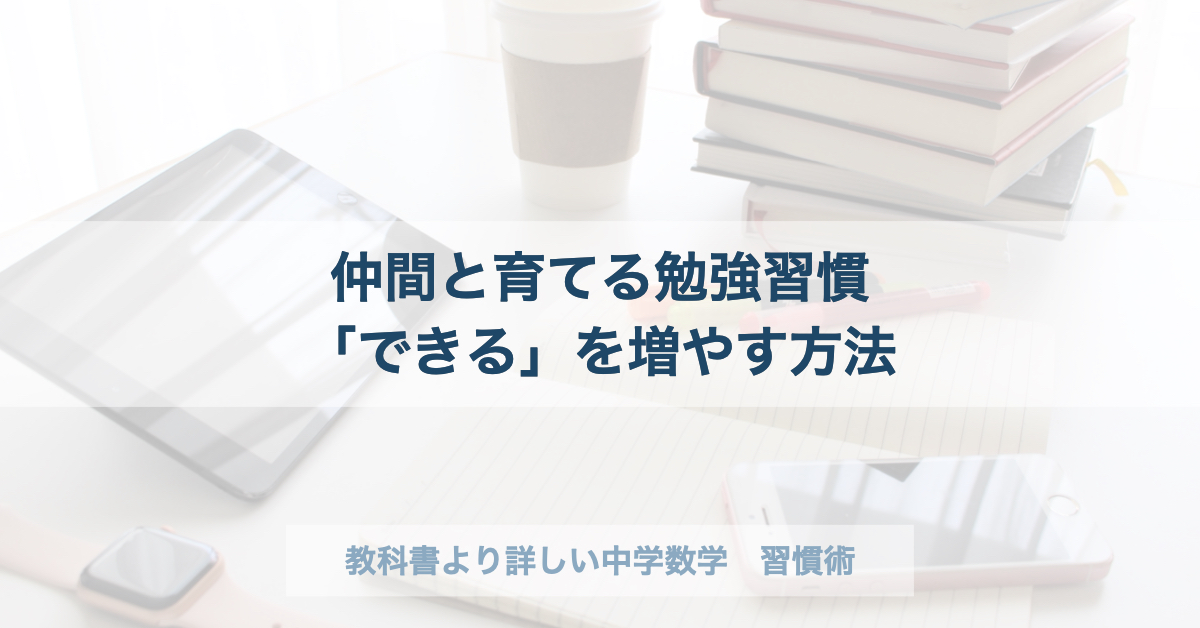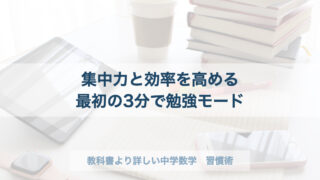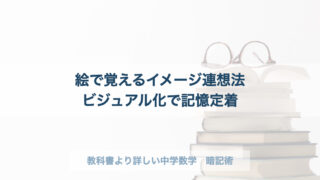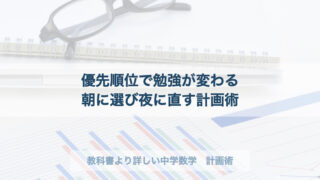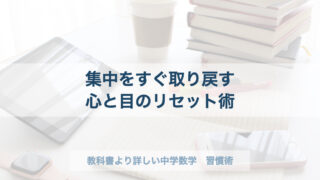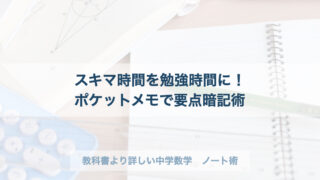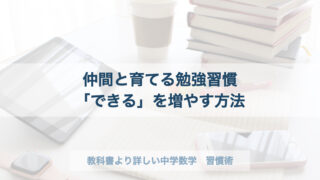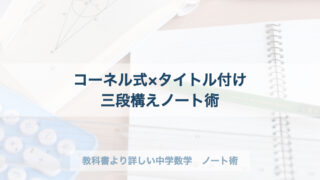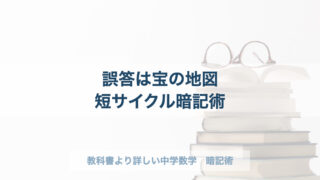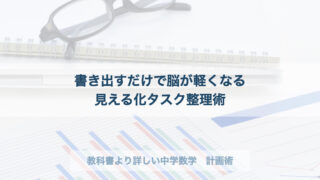一人だと続かないときは、友だちと学ぶ工夫、進み具合が見えるやり方、AIの安全な使い方、そして上手な質問が役に立ちます。今日から試せる形でまとめました。まずは一つだけやってみましょう。
友だちと一緒に学ぶコツ
- 5分ごとに「説明する人」と「聞く人」を交代する
- 25分勉強+5分休けいのリズムで続ける
- 最後に「今日できたこと」を一言で言い合う
友だちと勉強するときは、片方がずっと教えるのではなく、5分ごとに役わりを交代します。説明する人は「要点→例→注意」の順で短く話し、聞く人は「何がわかった?」「どこで迷った?」と2つだけ質問します。これだけで、だらだらしにくくなります。
時間は「25分勉強+5分休けい」の1セットにします。区切りがあると集中しやすく、勉強が苦手でも始めやすいです。休けいでは、良かったところをお互いに一つほめると、次のセットに入りやすくなります。
最後に「今日できたこと」を一言で言い合いましょう。例「平方完成で最大最小を説明できた」「弱酸のpHで先に条件を確認できた」。短く言えれば、頭の中が整理できています。スマホやノートに1行メモしておくと見直しに便利です。
チーム学習で続ける仕組み
- 週のはじめに小さな目標を決める
- 進み具合は「できた/あやしい/できない」で見える化
- 週末10分のふり返りで次の一歩をはっきりさせる
続けるコツは、小さく決めることです。「今週は例題を3つ」「この単元は“定義”だけ」など、手が届く目標にします。大きすぎる目標は続きません。
進み具合は、ノートの「問い」ごとに□(できた)△(あやしい)×(できない)をつけます。色ペンで塗ると、一目で弱点が分かります。次の勉強では、×から先にやり、△は「30秒で説明できるか」で仕上がりをチェックします。
週末の10分ふり返りは、紙1枚でOK。「うまくいった」「つまずいた」「来週ためすこと」を1行ずつ書くだけ。長い反省より、次に何をするかが大事です。新しい週は、その「ためすこと」からスタートしましょう。
AIを使った学び方(安全に)
- むずかしい説明の言いかえ、身近なたとえ、練習問題のたたき台に使う
- 使った後は、教科書や自分のノートで必ず確認する
- 出典や数字があやしいときは保留にして、大人や友だちに聞く
AIは、分かりにくい説明をやさしい言葉に直したり、身近なたとえを作ったりするのに便利です。練習問題のたたき台も作れます。ただし、まちがいがまざることがあります。
AIを使ったら、すぐに教科書やノートで確認しましょう。とくに数字や決まり(定義)は、教科書のページや授業プリントで照らし合わせます。合っていると分かってから使うのが安全です。
出典が言えない説明や、聞いたことのない用語が出たら、いったん保留に。先生や友だちに「ここだけ確認したい」とピンポイントで聞けば、短時間でモヤモヤを消せます。AIは「助け」として使い、最後の判断は自分の教材で行いましょう。
質問力を高める
- 「単語」ではなく「問いの文」で聞く
- 具体(場面や数)を入れて、的をしぼる
- もらった答えは1行でノートに残し、根拠と結びつける
質問は、ただ「定義は?」と聞くより、「密度は『何を割って』求める?」のように、動詞を入れた問いにします。「どんなときに使う?」「どこでまちがえやすい?」と、使い所や注意点を聞くのも効果的です。
具体を入れると、答えも具体になります。例「酢酸のpHを出すとき、先に何を確認する?」「因数分解で置換に切り替える合図は?」。場面や数があると、あいまいになりにくいです。
もらった答えは、ノートに1行で残します。「結論→一番の理由」を短く書き、となりに式や図のページを書いておくと、あとで見直す道すじがはっきりします。これを続けるほど、質問も復習も上手になります。
まとめ
- 5分交代のペア学習は、話す力も聞く力も伸びます。
- 小さな目標、3つのマーク(□△×)、週末10分のふり返りで、続けやすくなります。
- AIは言いかえや例づくりに便利。でも最後は教科書とノートで確認。
- 質問は「問いの文+具体」。答えは1行で残し、根拠とつなげるのがコツ。
この4つのうち、まず一つだけ今日ためしてみてください。明日、うまくいった点とむずかしかった点をそれぞれ1行で書ければ合格です。